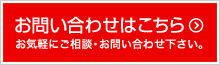伊勢神宮の丸太
FROM:山本洋
松阪の原木市場にて・・・
今回の原木市で、珍しい丸太が出ていたので買ってみました。

写真だけ見てもサッパリ分かりませんが、「伊勢神宮の丸太」だそうです。
伊勢神宮は外宮・内宮といった神社だけでなく、内宮の裏手に通称「神宮林」と呼ばれる山を持っています。
式年遷宮
ご存じかも知れませんが、伊勢神宮(正式には、ただ「神宮」とだけ言うのが正しいそうです)は20年に1回、全ての建物、装飾、宝物を作り替える「式年遷宮」という行事を行っています。
鳥居からお社から、本当に全て作り直すのですが、その時に大量の丸太が必要になります。
現在は、主に長野県の木曽にある御料林から調達しています。
壮大なスケール
ですが過去の資料を紐解くと、実はかつて(鎌倉時代とか)は神宮の裏手の山から伐っていたそうです。
逆に江戸時代以降は、参拝者向けに薪を切り出したりして荒れていったんだとか。
そんな中、「かつてのように、神宮の木は神宮から取れるようにしよう!」と、学者さんたちが知恵を出し合い、国を挙げて神宮の山づくりを始めました。
それがなんと大正の頃。
そして山づくりを始めて90年経って、ようやく平成25年の式年遷宮では、「一部の木」が神宮林から取ったそうです。
なんというスケール!これが日本人の山づくり。
物づくり大国ニッポンの源流は山づくりにある、と僕は確信しています。
一般の方お断り
で、その山づくりの際に間伐もします。
間伐といっても、そんな山ですから樹齢何十年という木も間伐するんですよね。
間伐された丸太は、そのまま捨てるのではなく、普段は入札にかけられるの「だそうです」。
・・・というのも、ここは関係者でないと入札にも入れない、特別な場所なのです。
ですので、伊勢市に工場があるわけでもない、隣町の製材所である僕なんかは、行ったことはありません。
ですが今回は、参加の権利を持っている松阪の原木市場が落札しました。
それを、一般の僕らが参加できる、松阪の原木市場で再度競りにかけた、というわけです。
で僕がそれを競り落としました。
神様の山
「神宮は総ヒノキづくりなのに、なんで杉の丸太が出てくるの?」
と思われたあなたは鋭い。
よく調べていないので推測の域を出ませんが、
神宮の山は神様の山。「儲かる山づくり」とはたぶん根本的に異なります。
使うのはヒノキだけど、杉も植え広葉樹も植え、多種多様な木を植えることで、
例えば病気や虫害に遭っても全滅しないとか、地滑りに強くなるとか。
複雑な生態系をはぐくむこととか。
お社以外にも、宝物なんかを作る材料としても考慮されているとか。
そういうことを考えて作られているのだと思います。
年輪は細かく、恐らくあまり余計な手を掛けず、天然に近い状態で育てているのだと思います。
そういう木は大抵、節が出やすいのですが、この木はどうなのか。
どうなるのか楽しみです。
だったらもっと高い値段で買えよ、とツッコまれそうですが・・・すんません、予算がないもので(;^_^A